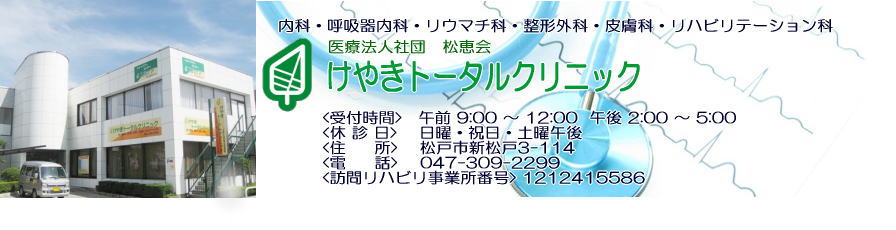老化とは? その2
老化はどのような機序で起こるのでしょうか?
以前より老化の原因に関する学説がいくつか提唱されており、次の古典的な6つの学説があります。
①プログラム説
寿命は遺伝子によって制御されており、老化は遺伝子にプログラムされているという説
②エラー説
DNA-RNA-蛋白合成系が突然変異や化学修飾により変調し、この集積によって細胞の機能障害、老化がもたらされるという説
③クロスリンキング説
複数の反応其をもつ物質が架橋となり、相異なる複数の高分子と結合して新しい高分子をつくることをcrosslinking(クロスリンキング)といいますが、こうした物質は分解されにくく、細胞障害をおこす可能性があり、このような物質の組織への沈着が老化の原因であるという説
④フリーラジカル説
スーパーオキサイド、過酸化脂質などの遊離電子をもつ分子(フリーラジカル)が蛋白、核酸、脂肪などの生体構成成分に障害を与え、細胞機能を低下させ老化を引き起こすという説
⑤免疫異常説
加齢に伴い、免疫担当細胞の機能低下により自己抗体が増加し、自己免疫反応が惹起されて老化がもたらされるという説
⑥代謝調節説
細胞の代謝回転が細胞分裂速度に影響して、老化や寿命を支配するという説
これらの学説は、それぞれ老化の本質の一面をとらえてはいますが、1つの学説で老化の機序を一元的に説明し得るものではありません。現在では、老化や寿命を決定している遺伝子があると考えられており、この意味では、先に述べたプログラム説が有力といえるでしょう。
しかし、老化は遺伝子によってのみ決定されるものではなく、環境因子(食事や運動、病気の有無など)によっても修飾されるので、これらの環境因子の管理をおろそかにするのは間違いでしょう。
老化とは? その1
そもそも老化とは、どういう状態をいうのでしょうか?
一般的に老化とは、成熟期以後、加齢とともに各臓器の機能、あるいはそれらを統合する機能が低下し、個体の恒常性を維持することが不可能となり、ついには死に至る過程と定義されるようです。
これに対し、加齢とは、生後から時間とともに個体に起こる、良いことも悪いことも含めた全ての過程や現象を指し、ネガティブなイメージの強い老化の概念と若干異なっています。
老化の特徴については①普遍性、②内在性、③進行性、④有害性の4つが挙げられます。すなわち、老化は誰にでも起こる現象であり、進行性で、個体の生存に対して有害に働き、その原因は主として個体に内在することを意味しています。